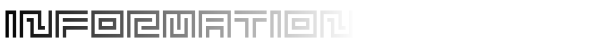01.31.01:41
[PR]
03.21.21:15
GSX-1300R クラッチフルード交換
久々の屋外ネタです。
しばらくまもろぐらしい記事がなかったので。。。
っていうか、隼をブログネタにするのも初めてなんですねぇ┐(´д`)┌
最近隼でフル加速をしたときに、クラッチが少しすべる感じがあって気になっていました。
また、今日になってフロントが浮きにくくなった気がしたので、重い腰を上げて作業します。
走行距離から見て、クラッチ板の磨耗はさほどでもないはずだから、とりあえず滑り対策にクラッチフルードの交換をすることにしたのですハイ。( ̄ー ̄)ニヤリ
さて、前置きが長いとみんな逃げちゃいそうなのでここらで本題です。

夜の作業なんで、見難かったらごめんなさい。(ーー;)
赤丸で示したカウルを外します。
赤丸が二つありますが、実はアンダーカウルと上のABS樹脂の黒いのは一体化してます。
ちょっと疲れてるんであんまり細かく書きませんぜ!(--;
カウルを外すと、ラジエーターサブタンクが現れるので、ネジ2本で外しちゃいます。

で、そのラジエーターサブタンクの裏(赤丸のあたり)にクラッチレリーズという部品があります。(^^)/

上記赤丸で示すニップルに用があるんです。
まずニップルのゴムキャップを外し、ホームセンターで買ってきたチューブ(長さ70cm以上)を差し込みます。
で、反対側を空のペットボトルなどに差し込みます。

まぁなければ8mmのメガネレンチでもいいけど。

それをこんな風に準備します。
つぎに、マスターシリンダーに付いてるサブタンクの周りを綺麗に掃除してからフタを開けます。
フタは3重になってます。
開けたとこ↓

深呼吸してから・・・

綺麗なウェスでリザーブタンク内を綺麗にします。
※埃や糸くずが出ないウェスを使ってくれよな!( ̄0 ̄)
あ…俺が写ってる・・・

こうやってかまえます。
左手はクラッチレバー、右手はフレアナットレンチを握る。
※ここから重要※
1、クラッチレバーを握って放すを3回以上繰り返す。
2、クラッチレバーを握ったまま、ニップルを90度くらい緩めてすぐ閉める。
3、クラッチを放す。
4、サブタンクのフルードの量を確認し、LOWラインまで減ったらフルードを追加する。
下から出るフルードが透明になるまで、上記1~4を繰り返します。
重要な注意は3つ!
①クラッチレバーを放してる状態では、絶対にニップルを緩めない!
②サブタンクを絶対空にしない!!
③サブタンクのフタを開けたままダイソーに電池を買いに行ったりしてはいけない!
この手順はブレーキフルードでも同じですからブレーキフルードの交換もしとけば?
俺はしないけどさ。
じゃ、友人Sが知りたそうなうんちく。
■ブレーキオイルじゃなくてブレーキフルード??
オイルとは石油系油脂を原材料としたもので、フルードはポリエチレングリコールモノエーテルを原材料としているものです。
現在はブレーキオイルというものはほとんど存在しません。(昔はあったけど)
上記2つは科学的液性が全く違うので、混ぜたりしてはいけません。
私が以前やった実験では、オイル(基油)とブレーキフルードを混ぜると、約2日後に濃緑色のヘドロが発生し、5日後には全体がどす黒く変色しました。
気泡や水分混入による白濁はありませんでしたが、部分的に粘性の高いヘドロがあるので油圧作動油には使用できないでしょう。
つまり、ブレーキフルードはオイルじゃないんです。
どちらかというとアルコールの方が近いかもしれません。
あ、そういえば、ブレーキフルードが手に付くと非常に熱く発熱します。
しかも、ポリエチレングリコールモノエーテルは非常に毒性が高く、飲用すると量によっては即死します。(※致死性については実験していません。友人Sで試してみようかな)
じゃ、明日ツーリングなんでこのへんで。
まもろぐでした~
しばらくまもろぐらしい記事がなかったので。。。
っていうか、隼をブログネタにするのも初めてなんですねぇ┐(´д`)┌
最近隼でフル加速をしたときに、クラッチが少しすべる感じがあって気になっていました。
また、今日になってフロントが浮きにくくなった気がしたので、重い腰を上げて作業します。
走行距離から見て、クラッチ板の磨耗はさほどでもないはずだから、とりあえず滑り対策にクラッチフルードの交換をすることにしたのですハイ。( ̄ー ̄)ニヤリ
さて、前置きが長いとみんな逃げちゃいそうなのでここらで本題です。
夜の作業なんで、見難かったらごめんなさい。(ーー;)
赤丸で示したカウルを外します。
赤丸が二つありますが、実はアンダーカウルと上のABS樹脂の黒いのは一体化してます。
ちょっと疲れてるんであんまり細かく書きませんぜ!(--;
カウルを外すと、ラジエーターサブタンクが現れるので、ネジ2本で外しちゃいます。
で、そのラジエーターサブタンクの裏(赤丸のあたり)にクラッチレリーズという部品があります。(^^)/
上記赤丸で示すニップルに用があるんです。
まずニップルのゴムキャップを外し、ホームセンターで買ってきたチューブ(長さ70cm以上)を差し込みます。
で、反対側を空のペットボトルなどに差し込みます。
倒れないようにねヽ(゚Д゚)ノ
で、今回のSSTフレアナットレンチ↓まぁなければ8mmのメガネレンチでもいいけど。
それをこんな風に準備します。
まだネジを緩めちゃだめですよ~◎(゚ロ゚)
つぎに、マスターシリンダーに付いてるサブタンクの周りを綺麗に掃除してからフタを開けます。
フタは3重になってます。
開けたとこ↓
うわぁ!! 黒!!(゚Д゚;)
深呼吸してから・・・
綺麗なウェスでリザーブタンク内を綺麗にします。
※埃や糸くずが出ないウェスを使ってくれよな!( ̄0 ̄)
あ…俺が写ってる・・・
こうやってかまえます。
左手はクラッチレバー、右手はフレアナットレンチを握る。
※ここから重要※
1、クラッチレバーを握って放すを3回以上繰り返す。
2、クラッチレバーを握ったまま、ニップルを90度くらい緩めてすぐ閉める。
3、クラッチを放す。
4、サブタンクのフルードの量を確認し、LOWラインまで減ったらフルードを追加する。
下から出るフルードが透明になるまで、上記1~4を繰り返します。
重要な注意は3つ!
①クラッチレバーを放してる状態では、絶対にニップルを緩めない!
②サブタンクを絶対空にしない!!
③サブタンクのフタを開けたままダイソーに電池を買いに行ったりしてはいけない!
この手順はブレーキフルードでも同じですからブレーキフルードの交換もしとけば?
俺はしないけどさ。
じゃ、友人Sが知りたそうなうんちく。
■ブレーキオイルじゃなくてブレーキフルード??
オイルとは石油系油脂を原材料としたもので、フルードはポリエチレングリコールモノエーテルを原材料としているものです。
現在はブレーキオイルというものはほとんど存在しません。(昔はあったけど)
上記2つは科学的液性が全く違うので、混ぜたりしてはいけません。
私が以前やった実験では、オイル(基油)とブレーキフルードを混ぜると、約2日後に濃緑色のヘドロが発生し、5日後には全体がどす黒く変色しました。
気泡や水分混入による白濁はありませんでしたが、部分的に粘性の高いヘドロがあるので油圧作動油には使用できないでしょう。
つまり、ブレーキフルードはオイルじゃないんです。
どちらかというとアルコールの方が近いかもしれません。
あ、そういえば、ブレーキフルードが手に付くと非常に熱く発熱します。
しかも、ポリエチレングリコールモノエーテルは非常に毒性が高く、飲用すると量によっては即死します。(※致死性については実験していません。友人Sで試してみようかな)
じゃ、明日ツーリングなんでこのへんで。
まもろぐでした~
PR
△このページ最上部へ
02.16.10:05
ETCアンテナの加工
めずらしく電子工作ネタです。
かなりいろんな物を作るんですが、人に見せるのは恥ずかしいのであんまり載せなんです(ーー;)
さて本題。
車用のETCをバイクに付ける場合、本体をシート下に、アンテナをメーター付近などに付けることになると思いますが、
カードの有無やエラーなどを表示するインジケーターランプが見えなくなるのが気になって改造してみました。
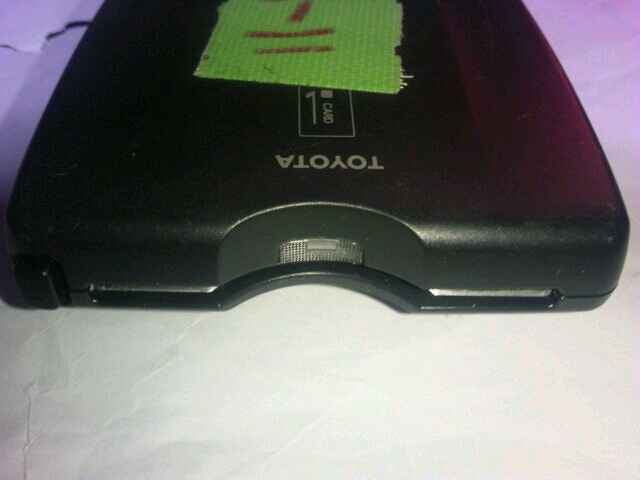
このETC端末は、スタンバイランプとエラーランプの2つが実装されています。
真ん中の部分が2色に光るわけですはい。
ではまずはアンテナを分解。
5.8Ghzアンテナモジュールが入っているかと思ったら、なんの変哲もないパッチアンテナが出てきました。
中身を取り出し、まずは筐体に穴を開けます。

2つのランプを内蔵したいので、2個開けました。
次に、この穴にエポキシを充填してレンズを作ります。
少し気泡を多めに入れて、光が拡散するようにしてみました!(^^)v

なんかロボットみたいでかわいいですね♪( ̄0 ̄)
エポキシが完全に固まったら、プライマーのあとにパールクリアを塗ってキラキラさせてみましたo(^-^)o
さて、開けた穴の間隔を参考に、LED基板を作成します。
使用したのは1608サイズのチップLEDです。
チップ部品は、瞬間接着剤で基板に貼っちゃうと半田付けが楽に出来ます。
写真の青いのは、仮止め用のグルーです(笑)

アンテナケーブルが長さ3メートルありますので、LED基板からETC本体までも、3メートルの細いケーブルでつなぎました。
写真を取り忘れましたが、パッチアンテナ基板とLED基板は防水のため樹脂コーティングしてあります。
透明の液体プラスチックを塗ってある感じですね。
ウレタン変性アクリルですので、10Ghz以上でも邪魔しませんし、陽が当たらなければ10年以上コーティングは持ちます。
で、こだわったのがシールです(^^)v
まずは耐水耐候フィルムにデザインを印刷し、カッティングプロッターでカット、そしてパールクリアでコーティングしました!
最近パールクリアにはまってますので、いろんな物に塗ってます(笑)

本当はポッティングしようと思ったのですが、時間がないのでパールクリアにしました。
って言っても、せっかくのプレゼントなので、3回重ね塗りしてます(≧Д≦)
かなりキラキラしてかわいいです。
ポッティングよりいいかもね♪(^^)/
失敗作が20枚くらい出来ちゃいましたけど(笑)
気に入ってくれるといいな!
あ、事後になりましたが、このブログの内容をマネする方は完全自己責任でお願いします。
法に触れたり、神の怒りをかうことがあっても管理人は一切責・・・もういいや。
続き読んで下さいな(v_v) △このページ最上部へ
かなりいろんな物を作るんですが、人に見せるのは恥ずかしいのであんまり載せなんです(ーー;)
さて本題。
車用のETCをバイクに付ける場合、本体をシート下に、アンテナをメーター付近などに付けることになると思いますが、
カードの有無やエラーなどを表示するインジケーターランプが見えなくなるのが気になって改造してみました。
このETC端末は、スタンバイランプとエラーランプの2つが実装されています。
真ん中の部分が2色に光るわけですはい。
ではまずはアンテナを分解。
5.8Ghzアンテナモジュールが入っているかと思ったら、なんの変哲もないパッチアンテナが出てきました。
中身を取り出し、まずは筐体に穴を開けます。
2つのランプを内蔵したいので、2個開けました。
次に、この穴にエポキシを充填してレンズを作ります。
少し気泡を多めに入れて、光が拡散するようにしてみました!(^^)v
なんかロボットみたいでかわいいですね♪( ̄0 ̄)
エポキシが完全に固まったら、プライマーのあとにパールクリアを塗ってキラキラさせてみましたo(^-^)o
さて、開けた穴の間隔を参考に、LED基板を作成します。
使用したのは1608サイズのチップLEDです。
チップ部品は、瞬間接着剤で基板に貼っちゃうと半田付けが楽に出来ます。
写真の青いのは、仮止め用のグルーです(笑)
アンテナケーブルが長さ3メートルありますので、LED基板からETC本体までも、3メートルの細いケーブルでつなぎました。
写真を取り忘れましたが、パッチアンテナ基板とLED基板は防水のため樹脂コーティングしてあります。
透明の液体プラスチックを塗ってある感じですね。
ウレタン変性アクリルですので、10Ghz以上でも邪魔しませんし、陽が当たらなければ10年以上コーティングは持ちます。
で、こだわったのがシールです(^^)v
まずは耐水耐候フィルムにデザインを印刷し、カッティングプロッターでカット、そしてパールクリアでコーティングしました!
最近パールクリアにはまってますので、いろんな物に塗ってます(笑)
本当はポッティングしようと思ったのですが、時間がないのでパールクリアにしました。
って言っても、せっかくのプレゼントなので、3回重ね塗りしてます(≧Д≦)
かなりキラキラしてかわいいです。
ポッティングよりいいかもね♪(^^)/
失敗作が20枚くらい出来ちゃいましたけど(笑)
気に入ってくれるといいな!
あ、事後になりましたが、このブログの内容をマネする方は完全自己責任でお願いします。
法に触れたり、神の怒りをかうことがあっても管理人は一切責・・・もういいや。
続き読んで下さいな(v_v) △このページ最上部へ
07.02.23:25
92' V-MAXのフロントフォークのオーバーホール
友達のVMAXのフロントフォークからオイルがにじんでたので、オイルシールとオイルの交換をすることにしました。
よく見るとダストシールはまだまだツヤも有り、なぜ漏れているのか謎でした。
ばらす前にダストシールを持ち上げてみると、あらら~。
オイルシールがサビだらけ(lll゚Д゚)

修理の前にネットで分解方法を探しても全く見つからない・・・。
こりゃあ苦労しそうだ。。。
梅雨の雨で作業が進まず・・・困っていると違う仕事が舞い込んできてまた進まず・・・。
屋根つきの整備場所が欲しいなぁ(涙)
晴れた隙を探して作業をすすめ、なんとか纏まりました。。
さて、持ち主への報告ブログです。
オイル放出↓

さらさら~っと出てきたオイルは、イチゴシロップ状のはずが・・・これじゃ汚れでおしるこだ(怖
ん??ん??
何じゃこりゃあ!!!
通常はサラダ油くらいの粘度なのに、これじゃあ味噌?!
鉄粉やら米麹やら油揚げの破片が混ざってひどい味噌汁になってます(ウソ
洗浄に苦労しそうだ。。。
分解に必要なSST。 作っちゃった↓

長いボルトの先にナットを溶接してSSTにしました。
予想以上にトルクがかかるようなのでしっかりと。。。

無事に分解が完了し、オイルシールを外したところ↓

アウター部に深い傷は見えず、なぜオイル漏れを起こしたのか分かりませんでした。
オイルシールも変な癖や傷は見当たらず、漏れた痕も見当たりません。。
とりあえずサビが異常に回り込んでいたので、1000番のサンドペーパーで磨きました。
サビはサビを呼ぶので、念入りに磨きましたとさ。
こんな感じ↓

その他全ての部品がヘドロまみれでこびりついてたので、洗浄するのに1時間はかかってしまいました。
パーツクリーナー5本と歯ブラシ3本、ワイヤーブラシ1本の浪費(涙)
オイルシールとフォークオイルのみ新品に交換し、その他はまだまだ使用出来そうだったので再使用です。
すべての部品の洗浄が終わったので、いよいよ組み立てです。
ごみの付着に気をつけながら組み立てました。。
が、なんだか気になって、一度新品のオイルですすぎました。
高いオイルがもったいないですが、あとで小さなごみに泣きたくないので、必要な浪費消費です。(´∀`;) 気弱・・・
安いオイルも用意しとけばよかった。。。orz
さて、新品のオイルを入れます。
今回使用したのは、国内最大手の会社の、フロントフォーク専用オイルです。
この会社とはちょっと取引があるので、ちょくちょくお世話になっています。
言っちゃあ悪いですが、かなり高級高性能なオイルです。
おとなしい走行環境なら、なんと30年交換不要だそうです!!
私のハヤブサに入れるために、精製したてフレッシュな物を横流し…じゃなくて譲ってもらいました(^^;
92' VMAXは油面は139mmですので、注射器を改造した物で正確に油面を合わせました。
んが、最後の最後に、インナーチューブに点錆があることに気が付きました。
もしかしてこの点サビがシールリップに傷を付けて漏れが出たのか・・・?
もっと早く気が付くべきだった(TT)
まぁ仕方ないので、サビ取り剤でインナーチューブを磨き、サビ止めコーティングを施しました。
工具やケミカル、オイルなど、結構出費がかさんでしまいました。
でもクレームになるのは嫌なので、まぁ必要経費でしょうかね。(大赤字ですが)
さて、試乗してみました。
この手のバイクはあまり乗りなれてないのですが、フロントがだいぶ反応がよくなりました。
無駄な振動や浮き沈みがなくなり、乗り心地が格段によくなりました。
ただ、リアショックがそうとうヘタってきてて、今すぐ交換したいくらいです。
リアだけふわふわしていて、夢心地~な感じ^^;
100km/h以上でギャップを踏んだらもうイッちゃいそう(汗)
前からそういう感じはあったそうですが、フロントフォークのOHを済ませたらさらに際立つようになってしまいました。
ってことで、次はリアショックの交換かOHすることになりそうかな??
まだフォークオイル交換だけでも4台控えてますので、しばらくはフォークオイルの匂いが体から抜けないかも(涙
使ったオイルは、契約している製油会社に特別高度に製油してもらっている物で、市販品とは比べ物にならない高品質なものに仕上がっています。(G-10規格)
バイクのフロントフォーク用に製造してもらっている物です。
多量に在庫ありますので、ご希望頂ければ100円/100mlでお譲りしますよ^^
ヤフオクで売ってる安物と比較してみてください。笑えますよ(笑)
△このページ最上部へ
よく見るとダストシールはまだまだツヤも有り、なぜ漏れているのか謎でした。
ばらす前にダストシールを持ち上げてみると、あらら~。
オイルシールがサビだらけ(lll゚Д゚)
修理の前にネットで分解方法を探しても全く見つからない・・・。
こりゃあ苦労しそうだ。。。
梅雨の雨で作業が進まず・・・困っていると違う仕事が舞い込んできてまた進まず・・・。
屋根つきの整備場所が欲しいなぁ(涙)
晴れた隙を探して作業をすすめ、なんとか纏まりました。。
さて、持ち主への報告ブログです。
オイル放出↓
さらさら~っと出てきたオイルは、イチゴシロップ状のはずが・・・これじゃ汚れでおしるこだ(怖
ん??ん??
何じゃこりゃあ!!!
通常はサラダ油くらいの粘度なのに、これじゃあ味噌?!
鉄粉やら米麹やら油揚げの破片が混ざってひどい味噌汁になってます(ウソ
洗浄に苦労しそうだ。。。
分解に必要なSST。 作っちゃった↓
長いボルトの先にナットを溶接してSSTにしました。
予想以上にトルクがかかるようなのでしっかりと。。。
無事に分解が完了し、オイルシールを外したところ↓
アウター部に深い傷は見えず、なぜオイル漏れを起こしたのか分かりませんでした。
オイルシールも変な癖や傷は見当たらず、漏れた痕も見当たりません。。
とりあえずサビが異常に回り込んでいたので、1000番のサンドペーパーで磨きました。
サビはサビを呼ぶので、念入りに磨きましたとさ。
こんな感じ↓
その他全ての部品がヘドロまみれでこびりついてたので、洗浄するのに1時間はかかってしまいました。
パーツクリーナー5本と歯ブラシ3本、ワイヤーブラシ1本の浪費(涙)
オイルシールとフォークオイルのみ新品に交換し、その他はまだまだ使用出来そうだったので再使用です。
すべての部品の洗浄が終わったので、いよいよ組み立てです。
ごみの付着に気をつけながら組み立てました。。
が、なんだか気になって、一度新品のオイルですすぎました。
高いオイルがもったいないですが、あとで小さなごみに泣きたくないので、必要な浪費消費です。(´∀`;) 気弱・・・
安いオイルも用意しとけばよかった。。。orz
さて、新品のオイルを入れます。
今回使用したのは、国内最大手の会社の、フロントフォーク専用オイルです。
この会社とはちょっと取引があるので、ちょくちょくお世話になっています。
言っちゃあ悪いですが、かなり高級高性能なオイルです。
おとなしい走行環境なら、なんと30年交換不要だそうです!!
私のハヤブサに入れるために、精製したてフレッシュな物を横流し…じゃなくて譲ってもらいました(^^;
92' VMAXは油面は139mmですので、注射器を改造した物で正確に油面を合わせました。
んが、最後の最後に、インナーチューブに点錆があることに気が付きました。
もしかしてこの点サビがシールリップに傷を付けて漏れが出たのか・・・?
もっと早く気が付くべきだった(TT)
まぁ仕方ないので、サビ取り剤でインナーチューブを磨き、サビ止めコーティングを施しました。
工具やケミカル、オイルなど、結構出費がかさんでしまいました。
でもクレームになるのは嫌なので、まぁ必要経費でしょうかね。(大赤字ですが)
さて、試乗してみました。
この手のバイクはあまり乗りなれてないのですが、フロントがだいぶ反応がよくなりました。
無駄な振動や浮き沈みがなくなり、乗り心地が格段によくなりました。
ただ、リアショックがそうとうヘタってきてて、今すぐ交換したいくらいです。
リアだけふわふわしていて、夢心地~な感じ^^;
100km/h以上でギャップを踏んだらもうイッちゃいそう(汗)
前からそういう感じはあったそうですが、フロントフォークのOHを済ませたらさらに際立つようになってしまいました。
ってことで、次はリアショックの交換かOHすることになりそうかな??
まだフォークオイル交換だけでも4台控えてますので、しばらくはフォークオイルの匂いが体から抜けないかも(涙
使ったオイルは、契約している製油会社に特別高度に製油してもらっている物で、市販品とは比べ物にならない高品質なものに仕上がっています。(G-10規格)
バイクのフロントフォーク用に製造してもらっている物です。
多量に在庫ありますので、ご希望頂ければ100円/100mlでお譲りしますよ^^
ヤフオクで売ってる安物と比較してみてください。笑えますよ(笑)
△このページ最上部へ
06.08.20:32
VMAX フロントのブレ
友人からVMAXの修理を依頼されたので記事にします。
沢山修理箇所はありそうですが、まずはフロントのブレの点検です。
低速でも高速でも、ほぼ全体にブレを感じます。
この症状で思いつくのは、アクスルベアリング、アクスルシャフト、ホイール、ブレーキディスクでしょうか。
まず簡単に、アクスルシャフトの曲がりや偏磨耗が無いかを点検することにしました。

まずはジャッキアップです。

この位置に木っ端を当て、持ち上げます。

次に、上記画像で示すネジを緩めます。
アクスルシャフトが緩んだら、反対側からドライバーなどでアクスルシャフトを叩きます。

アクスルシャフトが抜けると、スピードメーターギアが外れますので、そっと抜いてください。

ハイここで手順ミス!!
ブレーキキャリパーを外さないと、タイヤが抜けないんですね。。

これがアクスルシャフトです。
偏磨耗などはなさそうですが、グリス切れを起こしていました。
こういう場所には、リチウムグリスかウレアグリスがいいです。
っとその前に、レーザーで曲がりが無いか検査します。

あ!!! 曲がりはなさそうです(笑)
はぁあ。 アクスルシャフトじゃなかったか。
ってことは、ベアリングのガタツキかフロントフォークの曲がり??
丁度薄暗くなってきたので、レーザーにてフロントフォークの曲がりを検査しましょう。

どぉ?? 曲がってない??
うん大丈夫そう。。 って、一人の作業は寂しいので独り言・・・。
ここに書いた以外にもいろいろ分解検査しましたが、ここまでは異常は見られませんでした。
ってことは、あとはあれだよね。
あれ。↓

あれの続き→まもろぐ
△このページ最上部へ
沢山修理箇所はありそうですが、まずはフロントのブレの点検です。
低速でも高速でも、ほぼ全体にブレを感じます。
この症状で思いつくのは、アクスルベアリング、アクスルシャフト、ホイール、ブレーキディスクでしょうか。
まず簡単に、アクスルシャフトの曲がりや偏磨耗が無いかを点検することにしました。
まずはジャッキアップです。
この位置に木っ端を当て、持ち上げます。
次に、上記画像で示すネジを緩めます。
アクスルシャフトが緩んだら、反対側からドライバーなどでアクスルシャフトを叩きます。
アクスルシャフトが抜けると、スピードメーターギアが外れますので、そっと抜いてください。
ハイここで手順ミス!!
ブレーキキャリパーを外さないと、タイヤが抜けないんですね。。
これがアクスルシャフトです。
偏磨耗などはなさそうですが、グリス切れを起こしていました。
こういう場所には、リチウムグリスかウレアグリスがいいです。
っとその前に、レーザーで曲がりが無いか検査します。
あ!!! 曲がりはなさそうです(笑)
はぁあ。 アクスルシャフトじゃなかったか。
ってことは、ベアリングのガタツキかフロントフォークの曲がり??
丁度薄暗くなってきたので、レーザーにてフロントフォークの曲がりを検査しましょう。
どぉ?? 曲がってない??
うん大丈夫そう。。 って、一人の作業は寂しいので独り言・・・。

ここに書いた以外にもいろいろ分解検査しましたが、ここまでは異常は見られませんでした。
ってことは、あとはあれだよね。
あれ。↓
あれの続き→まもろぐ
△このページ最上部へ
09.12.02:17
SKYWAVEのプラグ交換
友人のskywave(CJ43A)が、低温時にエンストする・高回転時にボコ付くというので、プラグ交換をしてみました。
今までは元気だったようなので、この症状の場合は燃料系か点火系を疑うのが定説です。
先月、スロットルボディ・インジェクション等燃料系は完璧に掃除したので、今回は点火系をメンテすることにしました。
走行距離15,000kmとのことですので、丁度プラグ交換の時期です。
使用したプラグは、デンソーのIU24(イリジウムプラグ)です。
ついでですので、ハイテンションコードをスプリットファイヤに変えてみます。
時間が無い中での作業でしたので、写真が少なくてごめんなさい。
まず、左側(サイドスタンド側)のゴムマットを剥がします。
引っぱるだけでボツボツ剥がせますので、大小共に剥がしてください。
ゴムマットを剥がすと見えるネジ・ボルト・プラリベットを全部外します。
プラリベットは、黒い2重丸のような目玉焼きのような見た目をしています。
この中心(目玉焼きの黄身)をドライバーなどで押すと、4mm程度引っ込みます。
この状態で引き抜くと抜けます。(持ちずらいので少し苦労しますが)
次に、シート下のカバーを外します。(プラスネジ2本で固定されている)
さらに、給油口手前の黒いカバーも外します。
これはプラリベット2個だけで固定されていますが、その他ツメがたくさん止まっていますので、いろんな方向にゆがませて外してください。
結構勇気と力が要りますが、ABS樹脂ですのでかなり変形させても割れたりはしませんので大胆に行きましょう。
↓こんな状態

次に、サイドスタンドが見え隠れしているカウルを外します。
這い蹲って下から覗くと、このカウルを固定しているプラリベットが4個くらいあるので外します。(数が曖昧だ・・・)
全部のプラリベットが外れたら、カウルが外れます。
さて・・・ネジ類の数に圧倒されますね。。
たかがプラグ交換に20本近く外すなんて・・・スクーターは本当に面倒だ。。
後悔の念が出てきたので、ビタミンウォーターで休憩しました。。
レモン味のジュースが大好きな俺です。
さて、気を取り直して、下の写真を見てください。
赤丸で示す部分にプラグがあります。
写真ではすでにプラグキャップが抜かれ、プラグレンチが挿してありますね^^;

サイドスタンド側(つまり下側)から覗いた写真が↓です。

窮屈で回すのが大変。。
このプラグレンチはユニバーサルなので何とかなりましたが、そうじゃないプラグレンチだったら泣きたくなります。。
さてプラグの確認です。

左がIU24(新品)で右が外した物です。
あら。まだギャップ調整すれば使えそうだね。。
でもまぁ、せっかくなのでイリジウムにしましょう。
あ、そうそう。IU24はタイコ付きなので外すのを忘れずに。

コイルがこれまた外しにくい・・・もういや。

スプリットファイヤに交換。なんか変??気にしなくていいです。
たどり着くのは苦労しますが、交換作業はあっという間です。
完成写真はありません。
完成したら、5分くらい暖機運転してから20分くらい走りましょう。
FI車はコンピューター仕掛けですので、部品の交換を学習させなければいけませんので、この作業は必ず行ってください。
学習中は調子が悪いこともありますし、アイドリング回転数も異常かも知れませんが、学習が完了すれば本領が発揮されます。
交換後の結果ですが、完全に改善したそうです。
比較的無表情な友人ですが、ニタッって笑ってました。
直接的に褒めるようなセリフを吐かない奴ですが、表情で読取ると“満足”といった感じなのでOKとしましょう。
次はうちのフォルツァのプラグもやらなきゃっ
△このページ最上部へ
今までは元気だったようなので、この症状の場合は燃料系か点火系を疑うのが定説です。
先月、スロットルボディ・インジェクション等燃料系は完璧に掃除したので、今回は点火系をメンテすることにしました。
走行距離15,000kmとのことですので、丁度プラグ交換の時期です。
使用したプラグは、デンソーのIU24(イリジウムプラグ)です。
ついでですので、ハイテンションコードをスプリットファイヤに変えてみます。
時間が無い中での作業でしたので、写真が少なくてごめんなさい。
まず、左側(サイドスタンド側)のゴムマットを剥がします。
引っぱるだけでボツボツ剥がせますので、大小共に剥がしてください。
ゴムマットを剥がすと見えるネジ・ボルト・プラリベットを全部外します。
プラリベットは、黒い2重丸のような目玉焼きのような見た目をしています。
この中心(目玉焼きの黄身)をドライバーなどで押すと、4mm程度引っ込みます。
この状態で引き抜くと抜けます。(持ちずらいので少し苦労しますが)
次に、シート下のカバーを外します。(プラスネジ2本で固定されている)
さらに、給油口手前の黒いカバーも外します。
これはプラリベット2個だけで固定されていますが、その他ツメがたくさん止まっていますので、いろんな方向にゆがませて外してください。
結構勇気と力が要りますが、ABS樹脂ですのでかなり変形させても割れたりはしませんので大胆に行きましょう。
↓こんな状態
次に、サイドスタンドが見え隠れしているカウルを外します。
這い蹲って下から覗くと、このカウルを固定しているプラリベットが4個くらいあるので外します。(数が曖昧だ・・・)
全部のプラリベットが外れたら、カウルが外れます。
さて・・・ネジ類の数に圧倒されますね。。
たかがプラグ交換に20本近く外すなんて・・・スクーターは本当に面倒だ。。
後悔の念が出てきたので、ビタミンウォーターで休憩しました。。
レモン味のジュースが大好きな俺です。
さて、気を取り直して、下の写真を見てください。
赤丸で示す部分にプラグがあります。
写真ではすでにプラグキャップが抜かれ、プラグレンチが挿してありますね^^;
サイドスタンド側(つまり下側)から覗いた写真が↓です。
窮屈で回すのが大変。。
このプラグレンチはユニバーサルなので何とかなりましたが、そうじゃないプラグレンチだったら泣きたくなります。。
さてプラグの確認です。
左がIU24(新品)で右が外した物です。
あら。まだギャップ調整すれば使えそうだね。。
でもまぁ、せっかくなのでイリジウムにしましょう。
あ、そうそう。IU24はタイコ付きなので外すのを忘れずに。
コイルがこれまた外しにくい・・・もういや。
スプリットファイヤに交換。なんか変??気にしなくていいです。
たどり着くのは苦労しますが、交換作業はあっという間です。
完成写真はありません。
完成したら、5分くらい暖機運転してから20分くらい走りましょう。
FI車はコンピューター仕掛けですので、部品の交換を学習させなければいけませんので、この作業は必ず行ってください。
学習中は調子が悪いこともありますし、アイドリング回転数も異常かも知れませんが、学習が完了すれば本領が発揮されます。
交換後の結果ですが、完全に改善したそうです。
比較的無表情な友人ですが、ニタッって笑ってました。
直接的に褒めるようなセリフを吐かない奴ですが、表情で読取ると“満足”といった感じなのでOKとしましょう。
次はうちのフォルツァのプラグもやらなきゃっ
△このページ最上部へ